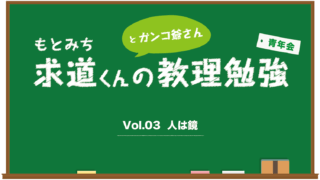中山家が、谷底を通っておられた頃のこと。ある年の暮れに、一人の信者が立派な重箱に綺麗な小餅を入れて、「これを教祖にお上げして下さい。」と言って持って来たので、こかんは、早速それを教祖のお目にかけた。
すると、教祖は、いつになく、
「ああ、そうかえ。」
と、仰せられただけで、一向御満足の様子はなかった。
それから二、三日して、又、一人の信者がやって来た。そして、粗末な風呂敷包みを出して、「これを、教祖にお上げして頂きとうございます。」と言って渡した。中には、竹の皮にほんの少しばかりの餡餅が入っていた。
例によって、こかんが教祖のお目にかけると、教祖は、
「直ぐに、親神様にお供えしておくれ。」
と、非常に御満足の体であらせられた。
これは、後になって分かったのであるが、先の人は相当な家の人で、正月の餅を搗いて余ったので、とにかくお屋敷にお上げしようと言うて持参したのであった。後の人は、貧しい家の人であったが、やっとのことで正月の餅を搗くことが出来たので、「これも、親神様のお蔭だ。何は措いてもお初を。」というので、その搗き立てのところを取って、持って来たのであった。
教祖には、二人の人の心が、それぞれちゃんとお分かりになっていたのである。
こういう例は沢山あって、その後、多くの信者の人々が時々の珍しいものを、教祖に召し上がって頂きたい、と言うて持って詣るようになったが、教祖は、その品物よりも、その人の真心をお喜び下さるのが常であった。
そして、中に高慢心で持って来たようなものがあると、側の者にすすめられて、たといそれをお召し上がりになっても、
「要らんのに無理に食べた時のように、一寸も味がない。」
と、仰せられた。