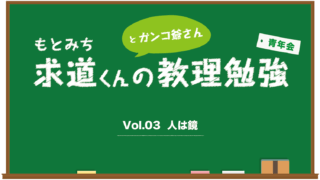Warning: Undefined variable $retHtml in /home/xs960841/takaoka56.com/public_html/wp-content/themes/jin-child/functions.php on line 149
文久三年七月の中頃、辻忠作の長男由松は、当年四才であったが、顔が青くなり、もう難しいという程になったので、忠作の母おりうが背負うて参拝したところ、教祖は、
「親と代わりて来い。」
と、仰せられた。それで、妻ますが、背負うて参拝したところ、
「ふた親の心次第に救けてやろう。」
と、お諭し頂き、四、五日程で、すっきりお救け頂いた。
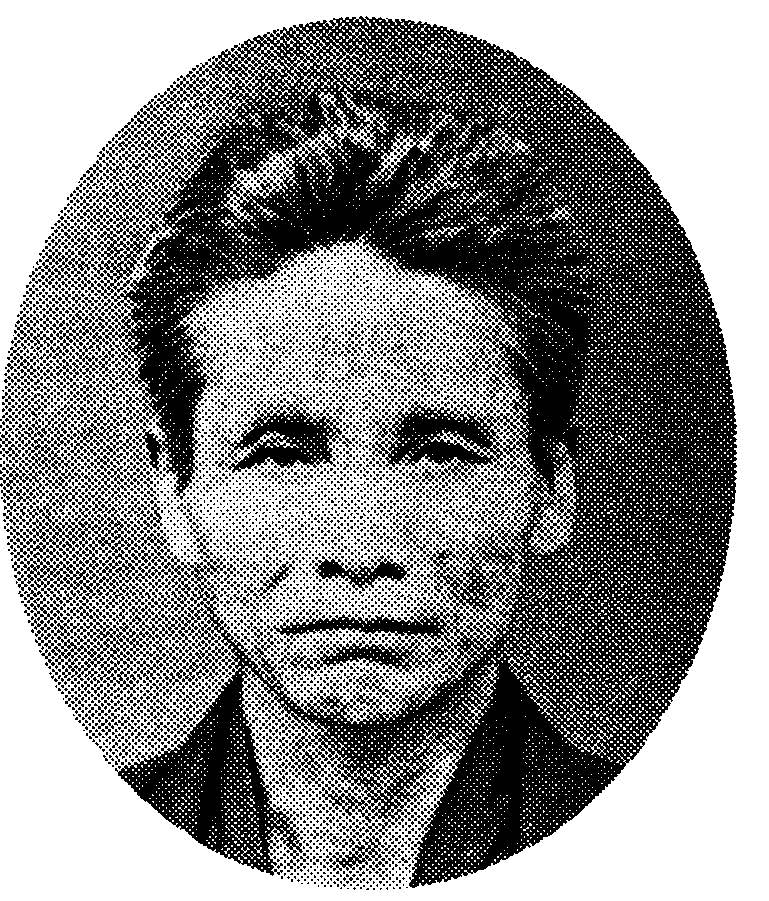
教祖(おやさま)から直接仕込みをうけた高弟の一人で幼名を忠右衛門と言う。天保7年(1836)大和国山辺郡豊田村(硯、奈良県天理市豊田町)に父忠作、母りう(おりう)の長男として誕生した。
父のしつけと生来の負けず嫌い、それに何事にも熱中する性格とが相まって、1年を3年分にも働くということで、千日さんと綽名されるほどの無類の働き者に成長し、23歳で家督を継ぎ忠作と名乗った。辻家には忠作という名前が3代にわたって受け継がれたようである。
忠作は妹くらの精神の患いをたすけられて教祖に心が向き、追うように長男由松の原因不明の高熱をたすけられて信仰の心を固めた。文久3年(1863)、忠作28歳のことである。
毎月26日、月に一度の参拝という形で開始された信仰は、やがて野良仕事がすめば夕食もそこそこに教祖の所へ通いつめて教えを受けるようになった。
元治元年(1864)には「肥のさづけ(さずけ)」を頂き、最初に「てをどり」(ておどり)の手ほどきを受けた。
忠作の信仰は、同じ豊田村の仲田儀三郎と競うように固められていき、明治6、7年頃には教祖のお供をするようになった。教祖とともに留置されたり、警察から信仰を止めるよう強要されたりしたが、動じるどころか、ますます信仰に熱が入り、履き替えの草鞋を2、3足も腰に結んで人たすけに歩き回り、ついには警官に「根限り信仰してみよ。その代わり本官も根限り止めてやる。」と言わせる程になった。
また、記憶力に優れ、事に触れては書き留めた忠作の手記は、天理教の初期の歩みを知る上で貴重な史料となっている。
明治19年(1886)の春から、教祖の指図によって家業を長男の由松に委せ、お屋敷に詰めて人々に親神の教えを取り次ぐようになった。一途で子供のように純真な人柄は多くの人々から慕われたが、明治38年(1905)7月12日、70歳の生涯を閉じた。
〔参考文献〕文教部宗教教育課編「先人手記抄」。三才社編『高弟列伝』第二編の中「辻忠作先生」。高野友治著『先人素描』(天理教道友社、昭和封年)。高野友治著『御存命の頃一改修版・上-』(天理教道友社)。辻忠作「ひながた」(『復元』31号)。諸井政一『改訂正文遺韻』。
ー天理教事典 第三版より抜粋ー
\ 辻忠作に関する記事 /
 6. 心を見て嘉永五年、豊田村の辻忠作の姉おこよが、お屋敷へ通うて、教祖からお針を教えて頂いていた頃のこと。教祖の三女おきみの人にすぐれた人柄を見込んで、櫟本の梶本惣治郎の母が、辻家の出であったので、梶本の家へ話したところ、話が進み、
6. 心を見て嘉永五年、豊田村の辻忠作の姉おこよが、お屋敷へ通うて、教祖からお針を教えて頂いていた頃のこと。教祖の三女おきみの人にすぐれた人柄を見込んで、櫟本の梶本惣治郎の母が、辻家の出であったので、梶本の家へ話したところ、話が進み、 57. 男の子は、父親付きで明治十年夏、大和国伊豆七条村の、矢追楢蔵(註、当時九才)は、近所の子供二、三名と、村の西側を流れる佐保川へ川遊びに行ったところ、一の道具を蛭にかまれた。その時は、さほど痛みも感じなかったが、二、三日経つと、大層腫れて来た
57. 男の子は、父親付きで明治十年夏、大和国伊豆七条村の、矢追楢蔵(註、当時九才)は、近所の子供二、三名と、村の西側を流れる佐保川へ川遊びに行ったところ、一の道具を蛭にかまれた。その時は、さほど痛みも感じなかったが、二、三日経つと、大層腫れて来た 62. これより東明治十一年十二月、大和国笠村の山本藤四郎は、父藤五郎が重い眼病にかかり、容態次第に悪化し、医者の手余りとなり、加持祈祷もその効なく、万策尽きて、絶望の淵に沈んでいたところ、知人から「庄屋敷には、病たすけの神様がござる。」
62. これより東明治十一年十二月、大和国笠村の山本藤四郎は、父藤五郎が重い眼病にかかり、容態次第に悪化し、医者の手余りとなり、加持祈祷もその効なく、万策尽きて、絶望の淵に沈んでいたところ、知人から「庄屋敷には、病たすけの神様がござる。」 65. 用に使うとて明治十二年六月頃のこと。教祖が、毎晩のお話の中で、 「守りが要る、守りが要る。」 と、仰せになるので、取次の仲田儀三郎、辻忠作、山本利八等が相談の上、秀司に願うたところ、「おりんさんが宜かろう。」という事になった。
65. 用に使うとて明治十二年六月頃のこと。教祖が、毎晩のお話の中で、 「守りが要る、守りが要る。」 と、仰せになるので、取次の仲田儀三郎、辻忠作、山本利八等が相談の上、秀司に願うたところ、「おりんさんが宜かろう。」という事になった。 166. 身上にしるしを明治十八年十月、苣原村(註、おぢばから東へ約一里)の谷岡宇治郎の娘ならむめ(註、当時八才)は、栗を取りに行って、木から飛び降りたところ、足を挫いた。それがキッカケとなってリュウマチとなり、疼き通して三日三晩泣き続けた。
166. 身上にしるしを明治十八年十月、苣原村(註、おぢばから東へ約一里)の谷岡宇治郎の娘ならむめ(註、当時八才)は、栗を取りに行って、木から飛び降りたところ、足を挫いた。それがキッカケとなってリュウマチとなり、疼き通して三日三晩泣き続けた。 191. よう、はるばる但馬国田ノ口村の田川寅吉は、明治十九年五月五日、村内二十六戸の人々と共に講を結び、推されてその講元となった。時に十七才であった。これが、天地組七番(註、後に九番と改む)の初まりである。 明治十九年八月二十九日、田川講元
191. よう、はるばる但馬国田ノ口村の田川寅吉は、明治十九年五月五日、村内二十六戸の人々と共に講を結び、推されてその講元となった。時に十七才であった。これが、天地組七番(註、後に九番と改む)の初まりである。 明治十九年八月二十九日、田川講元