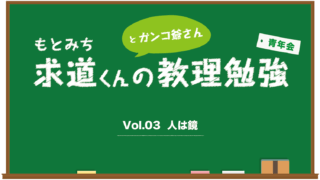明治五年、教祖が、松尾の家に御滞在中のことである。お居間へ朝の御挨拶に伺うた市兵衞、ハルの夫婦に、教祖は、
「あんた達二人とも、わしの前へ来る時は、いつも羽織を着ているが、今日からは、普段着のままにしなされ。その方が、あんた達も気楽でええやろ。」
と、仰せになり、二人が恐縮して頭を下げると、
「今日は、麻と絹と木綿の話をしよう。」
と、仰せになって、
「麻はなあ、夏に着たら風通しがようて、肌につかんし、これ程涼しゅうてええものはないやろ。が、冬は寒うて着られん。夏だけのものや。三年も着ると色が来る。色が来てしもたら、値打ちはそれまでや。濃い色に染め直しても、色むらが出る。そうなったら、反故と一しょや。
絹は、羽織にしても着物にしても、上品でええなあ。買う時は高いけど、誰でも皆、ほしいもんや。でも、絹のような人になったら、あかんで。新しい間はええけど、一寸古うなったら、どうにもならん。
そこへいくと、木綿は、どんな人でも使うている、ありきたりのものやが、これ程重宝で、使い道の広いものはない。冬は暖かいし、夏は、汗をかいても、よう吸い取る。よごれたら、何遍でも洗濯が出来る。色があせたり、古うなって着られんようになったら、おしめにでも、雑巾にでも、わらじにでもなる。形がのうなるところまで使えるのが、木綿や。木綿のような心の人を、神様は、お望みになっているのやで。」
と、お仕込み下された。以後、市兵衞夫婦は、心に木綿の二字を刻み込み、生涯、木綿以外のものは身につけなかった、という。
26. 麻と絹と木綿の話