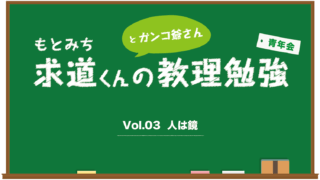明治十四年晩春のこと。ここ数年来、歯の根に蜂の巣のように穴があき、骨にとどいて、日夜泣き暮らしていた松井けい(註。当時三十一才)は、たまたま家の前を通りかかった鋳掛屋夫婦のにをいがけで、教えられた通り、茶碗に水を汲んで、
なむてんりわうのみこと
と唱えて、これを頂くと、忽ち痛みは鎮まり、二、三日のうちに、年来の悩みがすっかり全快する、というふしぎなたすけを頂いた。
そのお礼詣りに、磯城郡耳成村木原から、三里の道のりを歩いて、おぢばへ帰り、教祖にお目通りした。教祖は、三升の鏡餅を背負うて来た、当時八才の長男忠作に、お目をとめられて、
「よう、帰って来たなあ。子供には重荷やなあ。」
と、お言葉を下された。
忠作は、このお言葉を胸に刻んで、生涯忘れず、いかなる中も通り切って、たすけ一条に進ませて頂いた。
85. 子供には重荷