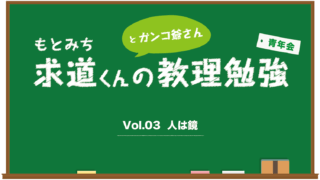教祖は、山中忠七に、
「神の道について来るには、百姓すれば十分に肥も置き難くかろう。」とて、忠七に、肥のさづけをお渡し下され、
「肥のさづけと言うても、何も法が効くのやない。めんめんの心の誠真実が効くのやで。」と、お諭しになり、
「嘘か真か、試してみなされ。」と、仰せになった。
忠七は、早速、二枚の田で、一方は十分に肥料を置き、他方は肥のさづけの肥だけをして、その結果を待つ事にした。
やがて八月が過ぎ九月も終りとなった。肥料を置いた田は、青々と稲穂が茂って、十分、秋の稔りの豊かさを思わしめた。が、これに反して、肥のさづけの肥だけの田の方は、稲穂の背が低く、色も何んだか少々赤味を帯びて、元気がないように見えた。
忠七は、「やっぱりさづけよりは、肥料の方が効くようだ。」と、疑わざるを得なかった。
ところが、秋の収穫時になってみると、肥料をした方の田の稲穂には、蟲が付いたり空穂があったりしているのに反し、さづけの方の田の稲穂は、背こそ少々低く思われたが、蟲穂や空穂は少しもなく、結局実収の上からみれば、確かに、前者よりもすぐれていることが発見された。

文政10年(1827)大和国式上郡大豆越村(現、桜井市大字大豆越)で、山中彦七、上里の二男として生まれる。
長男が早く亡くなったため家督をつぐ。山中家は近隣に聞こえた田地持ちで村の役職を務めていた。生来正直で働き者であった忠七は、その故をもって藩主から表彰されたこともあり、人びとの尊敬を集めていた。
文久2年(1862)、忠七36歳の時、平和な山中家に嵐のように不幸が襲った。その1年間に3度も葬式をした。それに加えて、妻の皇聖が長の病床に伏したのである。文久3年も暮れ、4年の正月を迎えたが、死を待つばかりの病人を抱えて山中
家の人びとは途方に暮れた。そんな時、すすめる人があって教祖におたすけを願うことになった。
「おまえは神に深いいんねんがあるから、神が引き寄せたのである。病気は案じることいらん。すぐにたすけてやるほどに。そのかわり、神のご用を聞かんならんで」というお言葉を頂き不思議な救済に浴した。これが山中家の信仰のはじまりであり、忠七が38歳の時である。
その後、忠七は熱心に信仰を続け、元治元年(1864)の「つとめ場所」の普請の時には費用を引き受けて尽力した。また、教祖から
「大豆越の宅は神の出張り場所」という言葉や、「これまで、おまえにいろいろ許しを渡した。なれど、口で言うただけでは分かろまい。神の道についてくるのに、物に不自由になると思い心配するであろう。なんにも心配することはいらん。不自由したいと思うても不自由しない確かな証拠を渡そう。」として、「永代の物種」を頂いている。天理教の草創時代、この道に深いかかわりをもって活躍し、明治35年11月22日、76歳で出直した。
〔参考文献〕大和真分教会『山中忠七伝』。
ー改訂 天理教事典より抜粋ー
\ 山中忠七に関する記事 /
 11. 神が引き寄せたそれは、文久四年正月なかば頃、山中忠七三十八才の時であった。忠七の妻そのは、二年越しの痔の病が悪化して危篤の状態となり、既に数日間、流動物さえ喉を通らず、医者が二人まで、「見込みなし。」と、匙を投げてしまった。この時、芝
11. 神が引き寄せたそれは、文久四年正月なかば頃、山中忠七三十八才の時であった。忠七の妻そのは、二年越しの痔の病が悪化して危篤の状態となり、既に数日間、流動物さえ喉を通らず、医者が二人まで、「見込みなし。」と、匙を投げてしまった。この時、芝 14. 染物ある時、教祖が、 「明朝、染物をせよ。」 と、仰せになって、こかんが、早速、その用意に取りかかっていた。 すると、ちょうど同じ夜、大豆越でも、山中忠七が、扇の伺によってこのことを知ったので、早速、妻女のそのがその用意を
14. 染物ある時、教祖が、 「明朝、染物をせよ。」 と、仰せになって、こかんが、早速、その用意に取りかかっていた。 すると、ちょうど同じ夜、大豆越でも、山中忠七が、扇の伺によってこのことを知ったので、早速、妻女のそのがその用意を 15. この物種は慶応二年二月七日の夜遅くに、教祖は、既にお寝みになっていたが、 「神床の下に納めてある壷を、取り出せ。」 と、仰せになって、壷を取り出させ、それから、山中忠七をお呼びになった。そして、お聞かせ下されたのに、 「これまで、
15. この物種は慶応二年二月七日の夜遅くに、教祖は、既にお寝みになっていたが、 「神床の下に納めてある壷を、取り出せ。」 と、仰せになって、壷を取り出させ、それから、山中忠七をお呼びになった。そして、お聞かせ下されたのに、 「これまで、 20. 女児出産慶応四年三月初旬、山中忠七がお屋敷で泊めて頂いて、その翌朝、教祖に朝の御挨拶を申し上げに出ると、教祖は、 「忠七さん、昨晩あんたの宅で女の児が出産て、皆、あんたのかえりを待っているから、早よう去んでおやり。」 と、仰せ
20. 女児出産慶応四年三月初旬、山中忠七がお屋敷で泊めて頂いて、その翌朝、教祖に朝の御挨拶を申し上げに出ると、教祖は、 「忠七さん、昨晩あんたの宅で女の児が出産て、皆、あんたのかえりを待っているから、早よう去んでおやり。」 と、仰せ 21. 結構や、結構や慶応四年五月の中旬のこと。それは、山中忠七が入信して五年後のことであるが、毎日々々大雨が降り続いて、あちらでもこちらでも川が氾濫して、田が流れる家が流れるという大洪水となった。忠七の家でも、持山が崩れて、大木が一時に埋没
21. 結構や、結構や慶応四年五月の中旬のこと。それは、山中忠七が入信して五年後のことであるが、毎日々々大雨が降り続いて、あちらでもこちらでも川が氾濫して、田が流れる家が流れるという大洪水となった。忠七の家でも、持山が崩れて、大木が一時に埋没 28. 道は下から 山中忠七が、道を思う上から、ある時、教祖に、「道も高山につけば、一段と結構になりましょう。」 と、申し上げた。すると、教祖は、 「上から道をつけては、下の者が寄りつけるか。下から道をつけたら、上の者も下の者も皆つきよ
28. 道は下から 山中忠七が、道を思う上から、ある時、教祖に、「道も高山につけば、一段と結構になりましょう。」 と、申し上げた。すると、教祖は、 「上から道をつけては、下の者が寄りつけるか。下から道をつけたら、上の者も下の者も皆つきよ 63. 目に見えん徳教祖が、ある時、山中こいそに、 「目に見える徳ほしいか、目に見えん徳ほしいか。どちらやな。」 と、仰せになった。 こいそは、「形のある物は、失うたり盗られたりしますので、目に見えん徳頂きとうございます。」 と、お答え申し
63. 目に見えん徳教祖が、ある時、山中こいそに、 「目に見える徳ほしいか、目に見えん徳ほしいか。どちらやな。」 と、仰せになった。 こいそは、「形のある物は、失うたり盗られたりしますので、目に見えん徳頂きとうございます。」 と、お答え申し 84. 南半国山中こいそが、倉橋村出屋鋪の、山田伊八郎へ嫁入りする時、父の忠七が、この件を教祖にお伺いすると、 「嫁入りさすのやない。南は、とんと道がついてないで、南半国道弘めに出す 。なれども、本人の心次第や。」 と、お言葉があった
84. 南半国山中こいそが、倉橋村出屋鋪の、山田伊八郎へ嫁入りする時、父の忠七が、この件を教祖にお伺いすると、 「嫁入りさすのやない。南は、とんと道がついてないで、南半国道弘めに出す 。なれども、本人の心次第や。」 と、お言葉があった 185. どこい働きに 明治十九年三月十二日(陰暦二月七日)、山中忠七と山田伊八郎が、同道でお屋敷へ帰らせて頂いた。 教祖は、櫟本の警察分署からお帰りなされて以来、連日お寝みになっている事が多かったが、この時、二人が帰らせて頂いた旨申し上げ
185. どこい働きに 明治十九年三月十二日(陰暦二月七日)、山中忠七と山田伊八郎が、同道でお屋敷へ帰らせて頂いた。 教祖は、櫟本の警察分署からお帰りなされて以来、連日お寝みになっている事が多かったが、この時、二人が帰らせて頂いた旨申し上げ