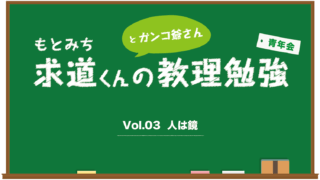加見兵四郎は、明治十八年九月一日、当時十三才の長女きみが、突然、両眼がほとんど見えなくなり、同年十月七日から、兵四郎もまた目のお手入れを頂き、目が見えぬようになったので、十一月一日妻つねに申し付けて、おぢばへ代参させた。教祖は、
「この目はなあ、難しい目ではあらせん。神様は一寸指で抑えているのやで。そのなあ、抑えているというのは、ためしと手引きにかかりているのや程に。」
と、仰せになり、つづいて、
「人言伝ては、人言伝て。人頼みは、人頼み。人の口一人くぐれば一人、二人くぐれば二人。人の口くぐるだけ、話が狂う。狂うた話した分にゃ、世界で誤ちが出来るで。誤ち出来た分にゃ、どうもならん。よって、本人が出て来るがよい。その上、しっかり諭してやるで。」
と、お諭し下された。つねが家にもどって、この話を伝えると、兵四郎は、「成る程、その通りや。」と、心から感激して、三日朝、笠間から四里の道を、片手には杖、片手は妻に引いてもらって、お屋敷へ帰って来た。教祖は、先ず、
「さあ/\」
と仰せあり、それから約二時間にわたって、元初まりのお話をお聞かせ下された。その時の教祖のお声の大きさは、あたりの建具がピリピリと震動した程であった。そのお言葉がすむや否や、ハッと思うと、目はいつとなく、何んとなしに鮮やかとなり、帰宅してみると、長女きみの目も鮮やかに御守護頂いていた。
しかし、その後、兵四郎の目は、毎朝八時頃までというものは、ボーッとして遠目は少しもきかず、どう思案しても御利やくない故に、翌明治十九年正月に、又、おぢばへ帰って、お伺い願うと、
「それはなあ、手引きがすんで、ためしがすまんのやで。ためしというは、人救けたら我が身救かる、という。我が身思うてはならん。どうでも、人を救けたい、救かってもらいたい、という一心に取り直すなら、身上は鮮やかやで。」
とのお諭しを頂いた。よって、その後、熱心におたすけに奔走するうちに、自分の身上も、すっきりお救け頂いた。
167. 人救けたら、