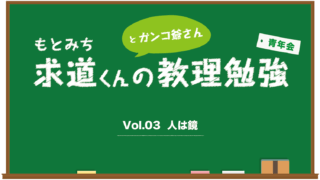大和国小阪村の松田利平の娘やすは、十代の頃から数年間、教祖の炊事のお手伝いをさせて頂いた。教祖は、
「おまえの炊いたものを、持って来てくれると、胸が開くような気がする。」
と、言うて、喜んで下された。お食事は、粥で、その中へ大豆を少し入れることになっていた。ひまな時には、教祖と二人だけという時もあった。そんな時、いろいろとお話を聞かせて下されたが、ある時、
「やすさんえ、どんな男でも、女房の口次第やで。人から、阿呆やと、言われるような男でも、家にかえって、女房が、貴方おかえりなさい。と、丁寧に扱えば、世間の人も、わし等は、阿呆と言うけれども、女房が、ああやって、丁寧に扱っているところを見ると、あら偉いのやなあ、と言うやろう。亭主の偉くなるのも、阿呆になるのも、女房の口一つやで。」
と、お教え下された。
やすは、二十三才の時、教祖のお世話で、庄屋敷村の乾家へ嫁いだ。見合いは、教祖のお居間でさせて頂いた。その時、
「神様は、これとあれと、と言われる。それで、こう治まった。治まってから、切ってはいかん。切ったら、切った方から切られますで。」
と、仰せられ、手を三度振って、
「結構や、結構や、結構や。」
と、お言葉を下された。
32. 女房の口一つ