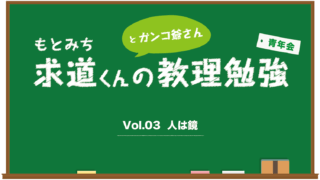明治七年十二月四日(陰暦十月二十六日)朝、増井りんは、起き上がろうとすると、不思議や両眼が腫れ上がって、非常な痛みを感じた。日に日に悪化し、医者に診てもらうと、ソコヒとのことである。そこで、驚いて、医薬の手を尽したが、とうとう失明してしまった。夫になくなられてから二年後のことである。
こうして、一家の者が非歎の涙にくれている時、年末年始の頃、(陰暦十一月下旬)当時十二才の長男幾太郎が、竜田へ行って、道連れになった人から、「大和庄屋敷の天竜さんは、何んでもよく救けて下さる。三日三夜の祈祷で救かる。」 という話を聞いてもどった。それで早速、親子が、大和の方を向いて、三日三夜お願いしたが、一向に効能はあらわれない。そこで、男衆の為八を庄屋敷へ代参させることになった。朝暗いうちに大県を出発して、昼前にお屋敷へ着いた為八は、赤衣を召された教祖を拝み、取次の方々から教の理を承り、その上、角目角目を書いてもらって、もどって来た。
これを幾太郎が読み、りんが聞き、「こうして、教の理を聞かせて頂いた上からは、自分の身上はどうなっても結構でございます。我が家のいんねん果たしのためには、暑さ寒さをいとわず、二本の杖にすがってでも、たすけ一条のため通らせて頂きます。今後、親子三人は、たとい火の中水の中でも、道ならば喜んで通らせて頂きます。」 と、家族一同、堅い心定めをした。
りんは言うに及ばず、幾太郎と八才のとみゑも水行して、一家揃うて三日三夜のお願いに取りかかった。おぢばの方を向いて、
なむてんりわうのみこと
と、繰り返し繰り返して、お願いしたのである。
やがて、まる三日目の夜明けが来た。火鉢の前で、お願い中端座しつづけていたりんの横にいたとみゑが、戸の隙間から差して来る光を見て、思わず、「あ、お母さん、夜が明けました。」 と、言った。
その声に、りんが、表玄関の方を見ると、戸の隙間から、一条の光がもれている。夢かと思いながら、つと立って玄関まで走り、雨戸をくると、外は、昔と変わらぬ朝の光を受けて輝いていた。不思議な全快の御守護を頂いたのである。
りんは、早速、おぢばへお礼詣りをした。取次の仲田儀三郎を通してお礼を申し上げると、お言葉があった。
「さあ/\一夜の間に目が潰れたのやな。さあ/\いんねん、いんねん。神が引き寄せたのやで。よう来た、よう来た。佐右衞門さん、よくよく聞かしてやってくれまするよう、聞かしてやってくれまするよう。」
と、仰せ下された。その晩は泊めて頂いて、翌日は、仲田から教の理を聞かせてもらい、朝夕のお勤めの手振りを習いなどしていると、又、教祖からお言葉があった。
「さあ/\いんねんの魂、神が用に使おうと思召す者は、どうしてなりと引き寄せるから、結構と思うて、これからどんな道もあるから、楽しんで通るよう。用に使わねばならんという道具は、痛めてでも引き寄せる。悩めてでも引き寄せねばならんのであるから、する事なす事違う。違うはずや。あったから、どうしてもようならん。ようならんはずや。違う事しているもの。ようならなかったなあ。さあ/\いんねん、いんねん。佐右衞門さん、よくよく聞かしてやってくれまするよう。目の見えんのは、神様が目の向こうへ手を出してござるようなものにて、さあ、向こうは見えんと言うている。さあ、手をのけたら、直ぐ見える。見えるであろう。さあ/\勇め、勇め。難儀しようと言うても、難儀するのやない程に。めんめんの心次第やで。」
と、仰せ下された。
その日もまた泊めて頂き、その翌朝、河内へもどらせて頂こうと、仲田を通して申し上げてもらうと、教祖は、
「遠い所から、ほのか理を聞いて、山坂越えて谷越えて来たのやなあ。さあ/\その定めた心を受け取るで。楽しめ、楽しめ。
さあ/\着物、食い物、小遣い与えてやるのやで。長あいこと勤めるのやで。さあ/\楽しめ、楽しめ、楽しめ。」
と、お言葉を下された。りんは、ものも言えず、ただ感激の涙にくれた。時に、増井りん、三十二才であった。
註 仲田儀三郎、前名は佐右衞門。明治六年頃、亮・助・衞門廃止の時に、儀三郎と改名した。
36. 定めた心