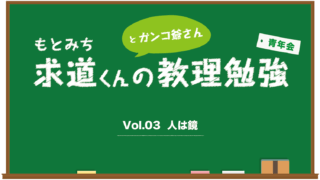抽冬鶴松は、幼少から身体が弱く、持病の胃病が昂じて、明治十二年、十六才の時に、危篤状態となり、医者も匙を投げてしまった。
この時、遠縁にあたる東尾の伝手で、浅野喜市が、にをいをかけてくれた。そのすすめで、入信を決意した鶴松は、両親に付き添われ、戸板に乗せてもらって、十二里の山坂を越えて、初めておぢば帰りをさせて頂き、一泊の上、中山重吉の取次ぎで、特に戸板のお許しを頂いて、翌朝、教祖にお目通りさせて頂いた。すると、教祖は、
「かわいそうに。」
と、仰せになって、御自身召しておられた赤の肌襦袢を脱いで、鶴松の頭からお着せ下された。
この時、教祖の御肌着の温みを身に感じると同時に、鶴松は夜の明けたような心地がして、さしもの難病も、それ以来薄紙をはぐように快方に向かい、一週間の滞在で、ふしぎなたすけを頂き、やがて全快させて頂いた。
鶴松は、その時のことを思い出しては、「今も尚、その温みが忘れられない。」 と一生口癖のように言っていた、という。
67. かわいそうに