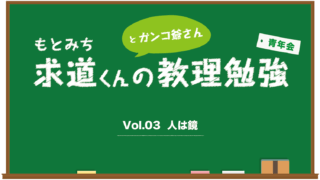明治十七年十月、その頃、毎月のようにおぢば帰りをさせて頂いていた土佐卯之助は、三十三名の団参を作って、二十三日に出発、二十七日におぢばへ到着した。
一同が、教祖にお目通りさせて頂いて退出しようとした時、教祖は、
「一寸お待ち。」
と、土佐をお呼び止めになった。そして、
「おひさ、柿持っておいで。」
と、孫娘の梶本ひさにお言い付けになった。それで、ひさは、大きな篭に、赤々と熟した柿を、沢山運んで来た。すると、教祖は、その一つを取ってみずから、皮をおむきになり、二つに割って、
「さあ、お上がり。」
と、その半分を土佐に下され、御自身は、もう一つの半分を、おいしそうに召し上がられた。やがて、土佐も、頂いた柿を食べはじめた。教祖は、満足げにその様子を見ておられたが、土佐が食べ終るより早く、次の柿をおむきになって、
「さあ、もう一つお上がり。私も頂くで。」
と、仰せになって、又、半分を下され、もう一つの半分を、御自分がお召し上がりになった。こうして、次々と柿を下されたが、土佐は、御自分もお上がり下さるのは、遠慮させまいとの親心から、と思うと、胸に迫るものがあった。教祖は、つづいて、
「遠慮なくお上がり。」
と、仰せ下されたが、土佐は、「私は、もう十分に頂きました。宿では、信者が待っておりますから、これを頂いて行って、皆に分けてやります。」と言って、自分が最後に頂いた一切れを、押し頂いて、懐紙に包もうとすると、教祖は、ひさに目くばせなされたので、ひさは、土佐の両の掌に一杯、両の袂にも一杯、柿を入れた。こうして、重たい程の柿を頂戴したのであった。
150. 柿